これから夏の暑い時期が始まりますが、市販のカリカリ梅も梅干しも大好きな方、いらっしゃいますか?
筆者は両方大好きです。さて、私が梅干し・カリカリ梅を作ろうと思ったきっかけは、
「最近何かと物価が高い上に、自分で市販品を買うのもいいけれど、昔のおばあちゃん世代のようになんでも手作りをすれば、体にもお財布にも優しいのではないだろうか?」
そう思った経緯で挑戦してみました!
この記事では、梅干し・カリカリ梅の作り方について、手順と体験談をご紹介していきます。
初心者の視点で「ここで失敗しそうになった!」というリアルな声もお届けするので、これから梅仕事を始めたいと思っている梅好きの方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね!
梅干し作りに必要な材料と道具

まずは、今回の梅干し作りに必要だった材料と道具は以下になります。
| 材料と道具 ・約1kgの青梅・塩(はかたの塩・天然塩)約150g・保存容器(今回は失敗リスクを考慮してジップロック使用)・消毒用焼酎・キッチンペーパー |
梅干し作りで最も大切なのは塩分濃度です。塩が少なすぎるとカビが生えやすいため、塩分が高いほど保存性は上がりますが、食べるときに塩抜きが必要になることもあるので注意しましょう。
一般的には、梅の重さの10〜18%の塩を使うのが目安です。
たとえば、1kgの梅を15%の塩分濃度にする場合だと以下の計算方法になります。
| 塩分濃度の計算方法 塩の量は、梅の重さ×0.15(15%) 1kg × 0.15 = 150g |
他にも、
・10% → 100gの塩
・15% → 150gの塩
・18% → 180gの塩
このような計算になります。
私は、梅干し作りが初心者なので、失敗を避けるために塩分濃度15%で作ることにしました。また、塩は「粗塩」や「天然塩」を使うとまろやかで美味しい仕上がりになります。
保存容器は、憧れの梅壺を使いたかったのですが、今回は失敗を考慮してジップロックにしました。
また、梅干し作りは雑菌との戦いでもあるので、道具はアルコールや熱湯でしっかり消毒してから使うことが大切です。
梅の下処理と漬け込みの手順

さて、ここでは梅の下処理と漬け込みの手順について5つの手順でご紹介していきます。
① 梅を洗う
スーパーで買ってきた青梅は、まずはざるに梅を入れたあとに水で優しく洗います。この際に、あまり力を入れてしまうと梅を傷付ける可能性があるので、優しく洗うことが大切です。
② 水気を拭き取る
洗ったあとの青梅は、一つずつ丁寧に水分をキッチンペーパーで拭き取ります。この際に、梅に水分が残っていると、カビの原因になりやすいので要注意!ヘタの隙間もていねいにチェックすることが大事です。また、この時点で傷んでいたり、凹んで茶色い部分がある梅は別で取り除き、梅ジャム用などにしましょう。
③ヘタを取る
次に、竹串で丁寧にヘタを取ります。筆者はこの工程が、スポッと簡単にヘタが取れて気持ちが良かったです。しかし、気を抜いてヘタを取り忘れがないように気を付けましょう。漬けたときに傷みやすいので、慎重に取り残しがないかチェックすることが大事です。
④梅干しを入れる容器を消毒
今回はジップロックを使用したため、私はジップロックをアルコール消毒した後にキッチンペーパーで拭きましたが、容器や壺を使う場合でも同様に消毒をして乾燥させましょう。ここでも、また水分が残っているとカビの原因になってしまうそうです…。
⑤塩漬けにする
いよいよ、梅と塩15%分を交互に層になるように並べ、塩をまんべんなく振りかけていきます。塩分が偏らないように、できるだけ均等にするのがコツです。今回は、ジップロックで漬けたので、重しは無しで空気を抜いて圧縮させました。容器や壺で梅干し作りをする場合は、ちゃんと重しを使いましょう!重しをすることで梅酢がしっかり上がり、雑菌の繁殖を防ぎます。
| 梅酢とは・・・ 梅を塩漬けにしたときに梅から自然にしみ出してくる水分のこと。もともと梅の実に含まれる水分が、塩の浸透圧によって引き出され、梅のエキスや酸味、塩分が溶け込んだ状態の液体になります。この梅酢には強い抗菌作用があり、梅干し作りの重要な役割を果たします。 (初心者の私は、梅干し作りをするまで、文字通りに梅から酢が出てくるものだと思ってしまっていました…笑) |
以上の手順を行ううえで、初心者の私は、正直なところ塩の量にとても迷いました。ジップロックだと、中身が見えて安心ですが、見えすぎて塩が足りなく見える現象が起きたのです。
「しょっぱくなりすぎないかな?」と不安でしたが、初心者はカビ防止のために多めの塩分が安心だと知り、若干後から追いで塩をこっそり入れてしまいました。
また、どうしても梅雨時期に常温で放置することに不安だった私は、冷蔵庫に入れて梅酢が上がるのを待つことにしました。
漬け込みからの経過と注意点
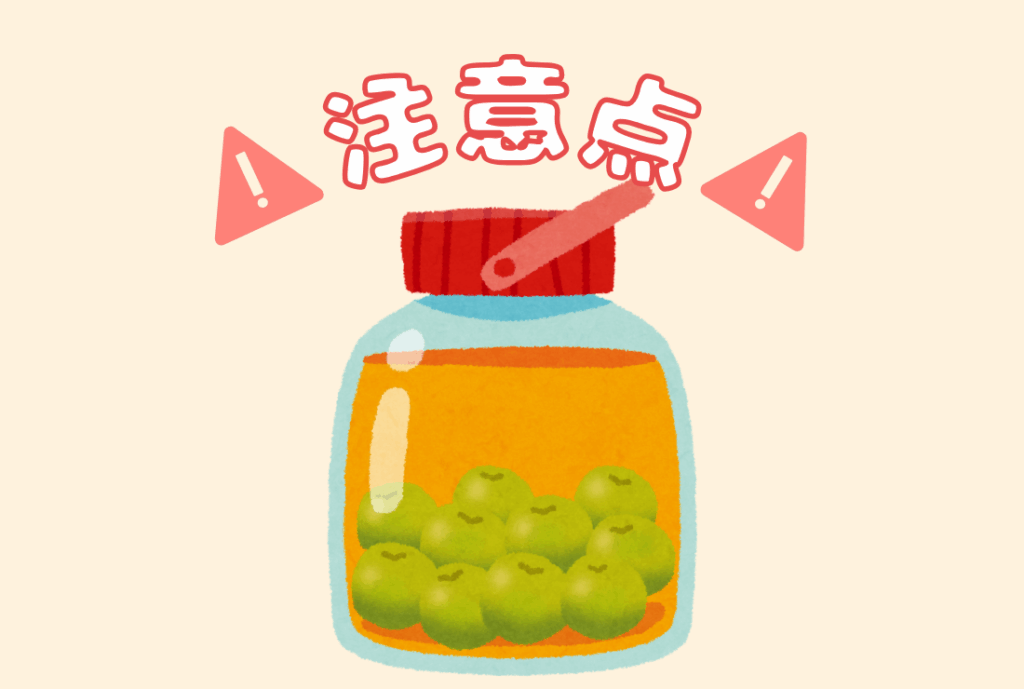
塩漬けが終わったあとは、梅酢がしっかり上がってくるかどうかが最大のポイントです。
重しを使う場合は数日で梅酢が上がってきますが、ジップロックの場合は空気を抜いて密閉した状態にすることで、梅の水分がしっかり出てきます。
私の場合は、梅を漬けてから3日ほどで、梅酢がじわじわと上がってきました。最初は水分が少ないのではと不安でしたが、梅から自然に出てくる水分でちゃんと漬け汁ができるんだと実感しました。
もし梅酢がうまく上がらない場合は、梅の表面が空気に触れたままだとカビが生えやすいので、焼酎を霧吹きで軽くスプレーして殺菌するのもおすすめです。
さらに、カビの発生を防ぐために、毎日中の様子をチェックして軽くゆすると安心です。
ジップロックで漬ける場合でも、ときどき袋を軽くもんだり上下をひっくり返したりして、塩分や梅酢が全体にいきわたるようにするとより失敗しにくいですよ。
初心者が気づいた梅仕事のポイント5つ

実際にやってみて、梅干し作りにはいくつか大事なポイントがあると感じました。
初心者だからこそ見えたポイントをまとめます。
・梅は傷や斑点のないきれいなものを選ぶ
傷んだ梅はカビの原因になりやすいです。
・塩分濃度は初心者なら15%がおすすめ
カビを防ぎやすく、安心感があります。
・道具はアルコールや熱湯でしっかり消毒
梅干し作りは雑菌との戦いです。
・漬けている間はこまめに様子を確認
梅の表面に白カビがないか、梅酢が足りない部分がないか毎日チェック。
・不安なら冷蔵庫漬けも選択肢に
夏の気温が高いときは冷蔵庫でも大丈夫。
こうした小さな気遣いをすることで、梅干し作りの失敗をかなり減らせると感じました。
【まとめ】梅仕事は簡単なようで難しいが、愛着が沸く分梅干しの完成が楽しみ

最初は「難しそう」「失敗したらどうしよう」と不安でしたが、実際にやってみると工程自体は意外とシンプルで、思った以上に取り組みやすく達成感がありました。
まだ漬け込みまでの段階ですが、自分で仕込んだ梅は、これからシソ漬けや梅雨明けの晴れた日に土用干しすることがとても楽しみです。
このあとも完成までしっかり見守っていきたいと思います。
これから梅干し作りに挑戦しようとしている方も、今年は一緒に梅干し作りを始めてみませんか?
最後まで読んでいただきありがとうございました。
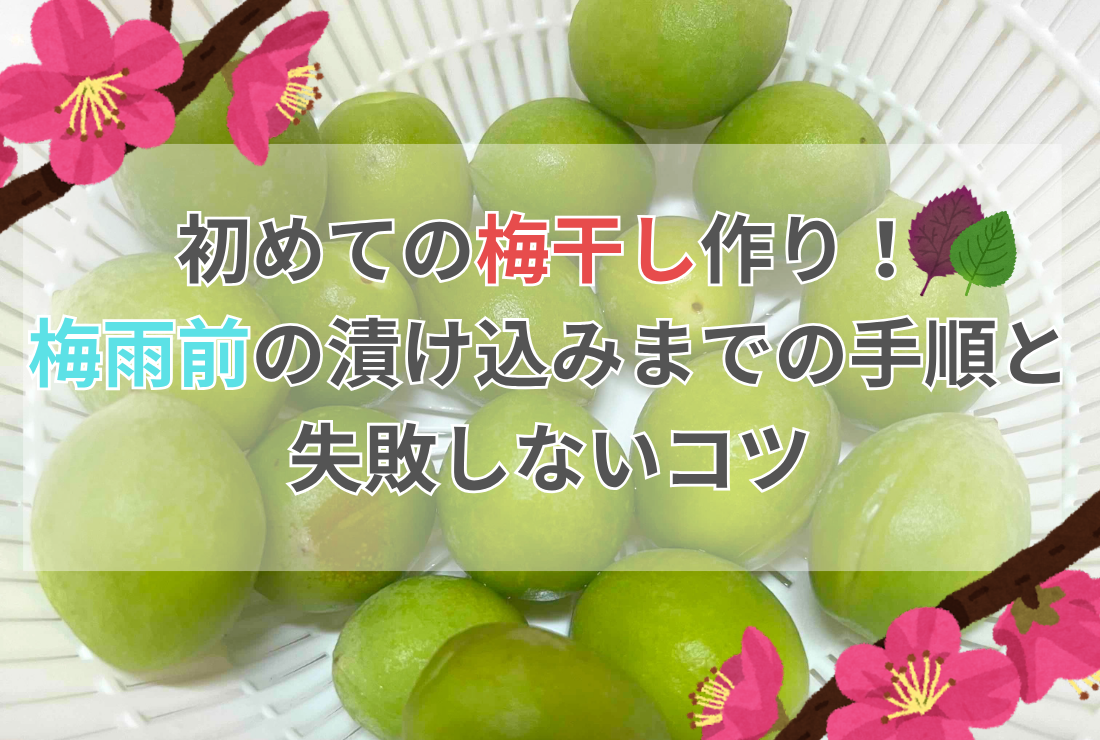
コメントを残す